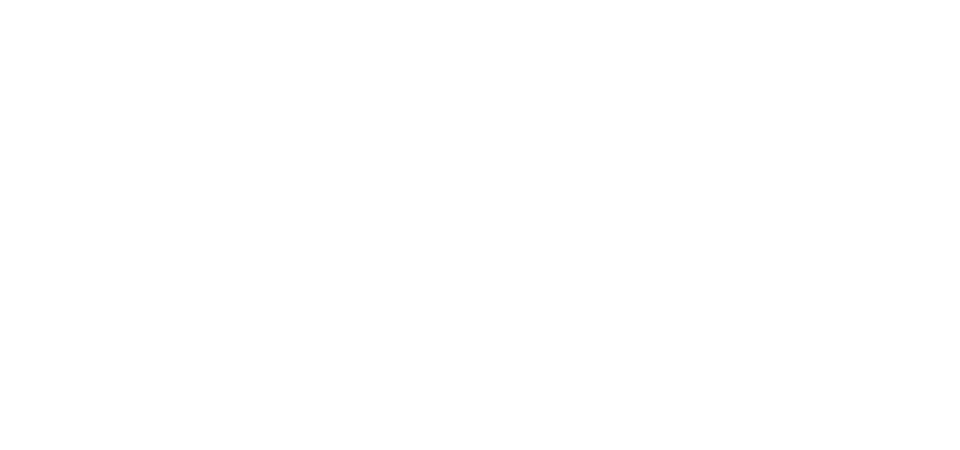
喪失と向き合う、グリーフケアについて
喪失と向き合う、グリーフケアについて
大切な人やものを失うことによって生じる、その人なりの自然な反応、感情、プロセスをグリーフと言います。このようなグリーフの感情やプロセスは自然なことと知ることで、自分を責めずに受け入れたり、感情の揺れを受け止めたりできます。それを知っておくことで、自身のセルフケアとなりうるかもしれませんし、周りの方の理解やサポートにつなげることもできますので、お伝えさせていただきます。
大切な人やものをなくす、というと、まず愛しい人との死別があります。が、それだけではなく、失恋や絶交、引越し(それまでの人間関係を失う)、ケガや病気(健康をそこなう)など、喪失を感じる大切なものは人それぞれです。幼い頃から大切にしていたぬいぐるみ、ということもあるでしょう。
大切な人やものをなくしたときの感情や反応は、悲しみ、やりきれなさ、後悔、怒り、安心(もう故人が痛みに苦しまなくていい、その苦しむ姿を見なくていい など)、無感動(あまりに辛い経験をしたとき心が動かない、閉ざしてしまう) などなど、人によってさまざまです。同じ人でも、時期によって違ってくることもあります。
そのグリーフの影響は多岐にわたります。
▷心理的影響:悲しみ、怒り、後悔、安堵、自責、無感動、無感覚、絶望感、など
▷身体的影響:睡眠や食欲への影響、胃痛、頭痛、めまいや吐き気、疲労や倦怠感、など
▷社会的影響:不登校、会社に行けない、人間関係の悪化、過活動(動いていることで保っている)、不信感、孤独感、孤立、など
▷スピリチュアル(一般的に使われる例的ということではなく、いのちの根源的なという意味)的影響:生きている意味の喪失や模索、神や仏など信仰への疑問、など
グリーフは、年数が経ってからでも落ち込むことはあります。命日や記念日、故人の好きだったものにふれたとき涙がでる、一緒に行った場所に行ったり見たりしたとき、思い出して懐かしく悲しくなる、などです。
このように、亡くなった人のことを思い出したり、失ったことについて考える、失ったことに思いを向ける時間と、新しい役割・生活に適応し仕事に励んだり、自分の時間を楽しんだり、自分の将来に向かって生きる、という回復志向の時間を、行ったり来たりして揺らぎながら喪失と向きあっていきます。このようにゆらげる方が喪失と向き合いやすいと言われています。失ったことに思いを向ける時間と、回復の時間、どちらの大事で、どちらにゆらいでもいいのです。
喪失から20以上経っても涙が出ることはあります。普段の生活の中では思い出さない時間の方が増えていても、ふと思い出して悲しくなることはあります。それは決してその人の心が弱いからではありません。
「大切な人をなくした人のための権利条約」
第1条 楽しんでいい 落ち込んでもいい
第2条 自分を許してもいい
第3条 考えない、思い出さないときもいい
第4条 自分を大切に
第5条 助けてもらうこと
第6条 みんなちがって、それぞれにいい
第7条 自分の人生を歩んでいい
この7カ条を心にとめ、感じたことに意識を向けながら一日一日を過ごしていきましょう。無理なく心地いいと思うこと、心の向くことをする。
感情や気持ちを表現してみるのもいいかもしれません。
好きな音楽を聴く・奏でる、絵を見る・描く、料理をする、写真を見る・撮る、誰かに話す、手紙や物語を書く、お墓参りをする、ご仏壇に手を合わせる、など。
なんだかやりきれない、話しを聞いて欲しい、一人でいたくない、など、お気軽にメールください。
資料「グリーフケア、サポートが当たり前にある社会の実現」を目指す一般社団法人 リヴオンより



